四季折々の美しい風景、 沿線の歴史・文化を象徴する
工芸や文化財、地元の恵みを生かした美食...。
西日本を巡り、人との出会いを通じて、
「瑞風」の旅を輝かせる “美” を発見します。


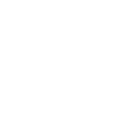
備前
土と水と火と風と
~先人を思い、素材と向き合う~
日本の自然、風土に作り手の感性を加え、800年もの時間をかけて、
世界的に見ても珍しい焼き締めの技法を進化させてきた「備前焼」。
TWILIGHT EXPRESS 瑞風のスイート客室と
3号車デッキのアルコーブをその作品で彩る備前焼作家として5人目の
人間国宝・伊勢﨑淳(いせざきじゅん)さんが
やきものの魅力、美しさの本質を語ります。
高校教師から陶芸の道へ
下関市の日和山公園に建つ高杉晋作の陶像を手がけたことで知られる名工・伊勢﨑陽山氏の次男として生まれた淳さんは、「家業は兄が継ぐから」と言われて育ったと話します。昭和11年(1936)生まれの伊勢﨑さんが青春期を過ごしたのは戦後。「やきものが売れない。備前にとって一番苦しい時代でした。やきものをする家は20軒ぐらいまでに減っていたと思います」。絵描きだった祖父と、父の工房に出入りする彫刻家や俳人の影響を受けていた伊勢﨑さんは、やがて岡山大学教育学部美術科に進学。片道2時間をかけ、4年間通ったものの、「在学中に、当時は鉄を使っていたオブジェ作家として今も活躍されている岡崎和郎さんと知り合い、現代美術の本がたくさんあるアトリエに足繁く通いました。大学にはただ単位を取りに行ったみたいなものでした」と笑います。




- 01-02釘を一本も使わずに建てた工房は新しい技法の実験場でもある。
- 03鉄分が抜け、よくなじんだ土を捏ねる。抜き型を使うなど、さまざまな技法が試されている。
- 04水にさらして粘土質だけを取り出し、2~3年寝かしておく。
大学卒業後は、父の薦めもあって高校の美術教師を務めていた伊勢﨑さん。いずれはやきものをしたいとの思いを胸に秘めつつ、跡取りである兄と父の手伝いをする程度にとどめていた頃、陽山氏が穴窯づくりをスタートさせます。「備前は、もともと穴窯で焼いていましたが、江戸末期に効率がいい登窯が主流になりました。けれども穴窯の方が表現の領域が幅広いやきものができる。つまり、作家性を追究したいと父は考えたのだと思います。ところが、窯が完成する直前、昭和36年(1961)の2月に病に臥せっていた父が亡くなりました。兄と僕で半地下式穴窯を完成させ、5月に初窯出しを行いました」。その少し前の3月、伊勢﨑さんは高校教師を退職していました。「反対する者がおらんようになったので、これからは好きな道に行こうと思った」と悪戯っぽく笑います。陶芸家への一歩を踏み出した瞬間でした。



- 05-06半地下式穴窯の内部。山の斜面に沿うようにつくられている。
- 07窯入れは年2回。油分の多い松の割木を1窯に1500束前後使用し、2週間かけて焼く。
高校教師の月給は当時12,500円。伊勢﨑さんはその1年分をつぎ込んで、現在工房や住まいを構えている土地を購入します。「今でこそ家が建ち並んでいますが、当時は国道2号線もJRの赤穂線も通っていない伊部の裏町。私が買った時、家は3軒しかありませんでした」。父、兄と共に築いた穴窯もすぐ近く。念願だったやきものに打ち込む日々が始まりました。
外の世界を知ることも大事
これまでに30回以上海外に出かけているという淳さんが、初めてヨーロッパを巡遊したのは35歳の時。「大学時代は現代美術に深い興味を抱いていましたし、それ以降もいろんなジャンルの美術に触れてきました。中でもスペインの画家・ミロが好きでね。そのことを知っている岡崎さんが、ミロを日本に紹介した美術評論家・瀧口修造さんに引き会わせてくれて、工房に行けるように手配してくれたのです」。ミロが制作した約50メートルもの陶壁がシンボルのバルセロナの空港に迎えに来てくれたのは、作品集を出版する会社の社長。その日はミロの仕事場で過ごしたと懐かしそうに話します。


優れた芸術家との交流から受けた刺激を糧にすることもあると明かす淳さんは、「でも、ものづくりの基本は素材」と話します。備前焼は釉薬を使いません。「ひよせ」と呼ばれる田の下の土を数年寝かせて陶土をつくり、時には成分の違う泥をかけたり、焼成時にくべる藁、割木の灰を活用して文様を浮かび上がらせます。代々受け継いできた伝統の技と作り手が編み出した技を駆使して造形と焼成を極めてこそ、いいやきものができる。その基本を踏まえた上で、「日本の豊かな自然や風土に作り手の感性や美意識を込めるためには、視野も広くなければ。限られた世界の中にいては、創作は前に進みません」。備前焼を外の世界から眺められたことも貴重な経験になったと振り返ります。
美の本質は自然の中に
「瑞風」の車内には伊勢﨑さんの作品が3点展示されています。その1つ、代表作でもある「角花入」は人をかたどった作品です。「原点になっている、スタチューと名づけた花入があるのですが、上部に3つの穴があって顔を表しています。「瑞風」で見ていただけるのはその進化形。同じく人を表しています。上部が肩、2つに分かれているボトムは足です」。車内では、備前の土の色をそのまま生かした茶系の花入と、備前の隣町である長船で採れる鉄分の多い泥をかけて焼いた花入、2つの異なる作風が楽しめます。


- 08代表作である「角花入」。備前の土そのままの色を活かした作品。
- 09「瑞風」車内に展示されている、泥をかけて焼いた角花入。
同じ角花入で、ハート型の文様が浮かび上がっている作品も発表されています。「粘土の板をつくって、松割り木の灰がかからないようにするんです。そうすると影になる部分ができ、ハート型が浮かび上がってくる。1箇所だけでは面白くないから、もう1つハートをつくり、グラデーションにする。これはすべて計算。窯入れの時、どの場所に作品を置いて、火と風を狙い定めて当てるように焼いていくわけです」。伊勢﨑さんは惜しげもなく創作秘話を明かしてくれました。


- 10松割り木の灰が飛んでできる「ごま」と、藁の成分が付着してできる赤い線「火だすき」が見られる壺。
- 111200℃の窯から素早く取り出すことで青っぽい色にする「引き出し黒」茶碗。
伊勢﨑さんが15~16年前に考案した。
「原土を取ってきて、寝かせて陶土をつくる。水を加えて成形し、油っ気の多い松割り木を焚いて、風を起こし、流れを変えて酸化・還元を誘発させ、色を変える。水分がほしい時は濡れた割り木をくべる。割り木の灰がかかると、ごまと呼ばれる自然釉が生じ、いい味になるわけ。不測の事態も起こりますよ。でもそれも長年の経験に基づいて乗り越える。目には見えない努力もたくさんしなければなりません。それが備前焼。土と水と火と風、自然の要素に本質を求めるのです」。窯焚きが始まると2週間近く、不眠不休の日々が続きます。
-

12 -

13 -

14 -

15 -

16
- 12-16つくりたいものに合わせて道具も自分でつくるのが、伊勢﨑さんの流儀。
高度成長期にブームを呼んだ備前焼。新幹線の開通やバブル期もあり、一時は商店などが急増しましたが、伊勢﨑さんによると今は300軒程度で推移しているそうです。他府県から修業に来る若者も多く、伊勢﨑さんの工房でも3人が制作に勤しんでいます。「基本の仕事を教えて、いろんな作業を手伝ってもらうんだけれども、午後5時以降は自由時間。何をしてもいいことにしています」。伊勢﨑さん自身がそうだったように、作家として歩むためには、先人の努力の跡をしっかり学ぶと同時に、独自性を高めねばなりません。「だから、土も窯も道具も自分でつくってこそ、独自の作品が生み出せるのだと思います」。80歳を過ぎてなお情熱を絶やさず、プロジェクションマッピングといった現代技術とのコラボレーションにも積極的な姿勢には驚かされます。伝統へのリスペクトとイノベーティブな精神。その双方が美しい焼物を世に送り出す原動力です。
 生まれ育った岡山をはじめ、美しい自然が残る中国地方の魅力や地域固有の文化を、「瑞風」乗車の機会にぜひ感じていただきたいと思っています。また、数多くの美術品が彩る特別な車内に私のやきものがあることを光栄に感じると共に、少しでも多くの方の目に留まれば嬉しいと思います。あまり大それたことは言えませんが、備前では他の土地から移り住んできた者も含め、多くの陶工が鎬を削って作品作りに邁進しています。1200℃の高温で焼き上げる唯一無二の存在「備前焼」を知っていただける好機になれば幸いです。
生まれ育った岡山をはじめ、美しい自然が残る中国地方の魅力や地域固有の文化を、「瑞風」乗車の機会にぜひ感じていただきたいと思っています。また、数多くの美術品が彩る特別な車内に私のやきものがあることを光栄に感じると共に、少しでも多くの方の目に留まれば嬉しいと思います。あまり大それたことは言えませんが、備前では他の土地から移り住んできた者も含め、多くの陶工が鎬を削って作品作りに邁進しています。1200℃の高温で焼き上げる唯一無二の存在「備前焼」を知っていただける好機になれば幸いです。